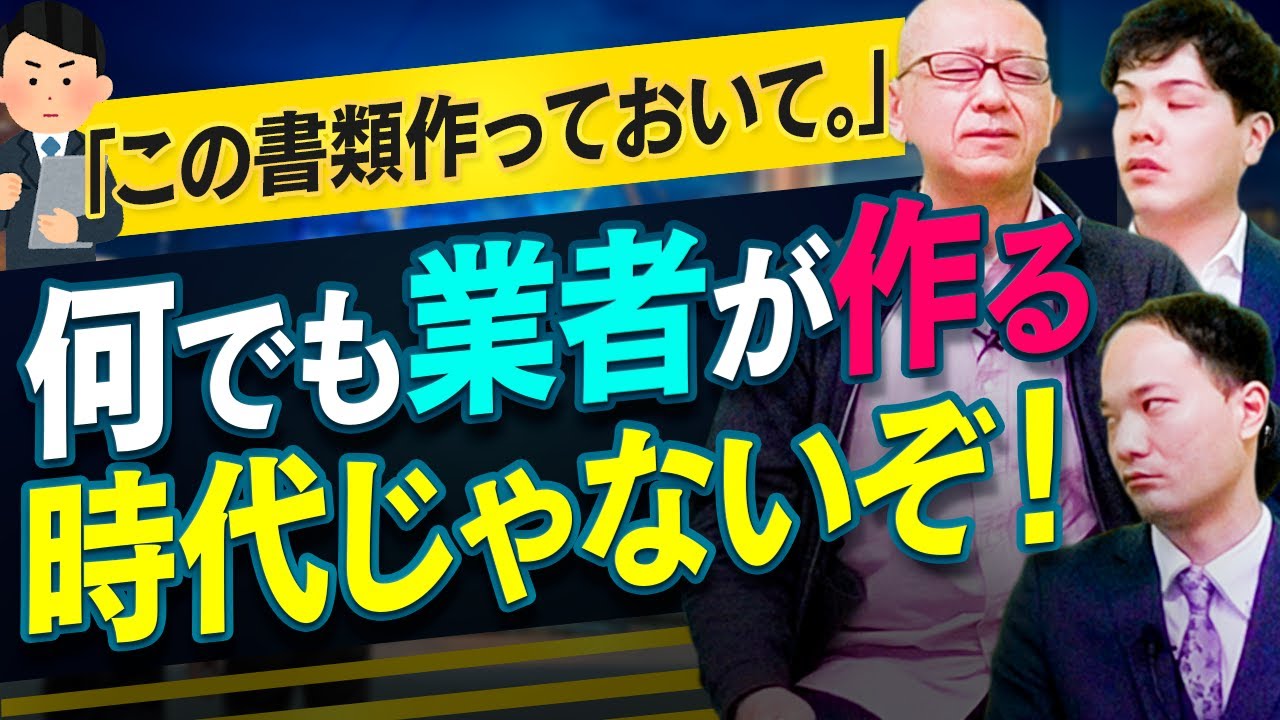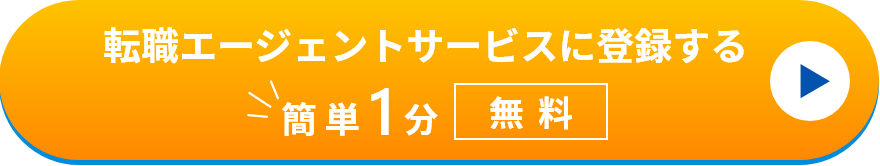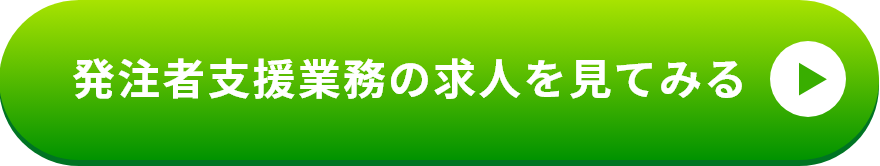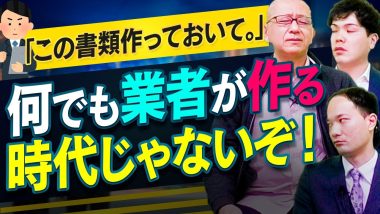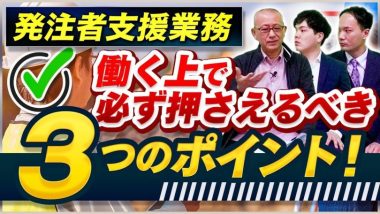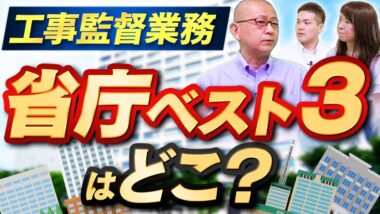書類確認も楽になる!?工事書類スリム化の主な取り組みを押さえよう
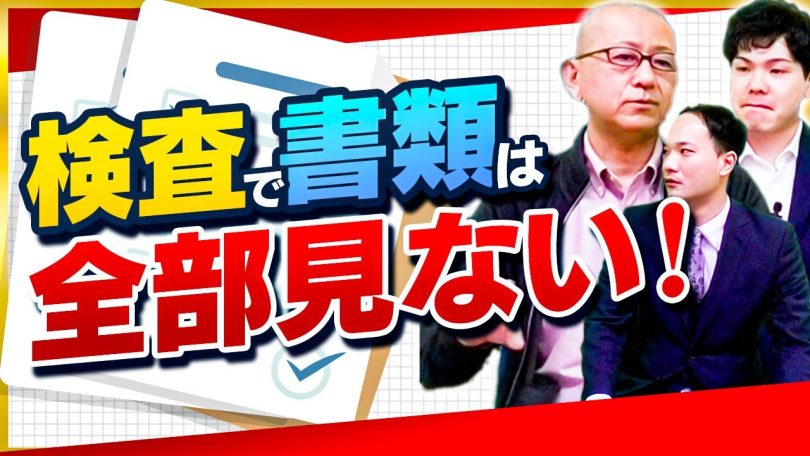
この記事は以下の記事の続きです。
前の記事を読んでいない方は、こちらの記事もご覧ください。
国土交通省では、工事書類を必要最小限にスリム化(簡素化)するため、さまざまな取り組みを行っています。
またその取り組みをまとめた土木工事電子書類スリム化ガイドが令和3年に改定され、内容がよりブラッシュアップされました。
今回は前記事に引き続き、同ガイドの内容に沿って、工事書類の扱いがどのように変化しているのか具体的に解説します。
なお、前回紹介した取り組みは次の3つです。
- 工事着手前の設計審査会で役割分担を明確化
- 施工計画書の提出と内容について
- 工事打合せ簿の添付資料について
発注者支援業務は工事書類をチェックする立場ですので、ぜひこの記事を参考に、簡素化の動きを押さえていきましょう!
目次
簡素化の取り組み4: 施工体制台帳の添付資料は必要最小限にする

施工体制台帳とは、施工を請け負うすべての業者や施工範囲、各責任者などを明記した台帳のことです。
施工に関する体制を記載した台帳=施工体制台帳ということですね。
これまで施工体制台帳の提出時には、次のような証明書類を添付するのが通例でした。
- 建設業許可や警備業認定証の写し
- 請負会社の厚生年金保険や雇用保険加入を証明するものの写し
- 監理技術者などの技術者届の写し
- 見積依頼書の添付図面
- 技術者配置要件以外の資格や実務経歴の写し
しかし今後、この種の書類は添付不要となります。
特に建築では業者の出入りが多いため、書類添付の手間も大変なものでしたが、その点が簡素化されたということになります。
施工体制台帳の添付書類は減らされはしましたが、建設業法施行規則第14条の2第2項に則り、下記の書類は引き続き添付必須となります。
- 発注者との契約書の写し
- 下請負人が注文者との間で締結した契約書の写し(注文・請書及び基本契約書又は約款等の写し)
- 元請負人の配置技術者が主任(監理)技術者資格を有することを証する書面(監理技術者は、監理技術者資格証の写しに限る)
- 監理技術者補佐を置いた場合は、監理技術者補佐資格を有することを証する書面
- 専門技術者を置いた場合は、資格を有することを証する書面(国家資格等の技術検定合格証明証等の写し)
- 主任(監理)技術者、監理技術者補佐及び専門技術者の雇用関係を証明できるものの写し(健康保険証等の写し)
施工体制台帳に作業員名簿の添付書類は不要
施工体制台帳に添付すべき書類の1つとして、作業員名簿があります。
作業員名簿とは、工事現場に出入りする作業員達を把握・管理するための書類です。
様式は、一般社団法人全国建設業協会がまとめたものが基本となっていますが、元請けの会社が独自に用意している場合もあります。
主に設けられているのは次のような項目です。
- 氏名
- 生年月日
- 年齢
- 職業
- 社会保険(雇用・健康・年金)の加入状況
- 資格・免許
- 入場年月日
- 受入教育実施年月日
- 作業員の区分(現場代理人・主任技術者・職長・作業主任者・女性作業員・18歳未満の作業員・外国人技能実習生・外国人建設就労者など)
作業員名簿は引き続き提出が必要とされますが、添付書類は不要となります。
たとえば作業員達の運転免許証のコピーなど、各人の資格・免許を示すための添付書類は必要ありません。
施工管理台帳については従来、さまざまな書類が添付されてきたのですが、それが総じて不要となったイメージですね。
簡素化の取り組み5: 臨場確認の写真は添付不要

臨場とは、施工現場へ実際に赴き、施工の段階、仕様通りの材料を使用しているかの確認や、立会いを行うことです。
これまでは国土交通省の職人や発注者支援業務を行う現場技術員が臨場しているという証拠を示すために、施工会社側が確認状況を写真に収め、確認書に添付するのが通例となっていました。
しかし臨場時の状況写真は不要とされ、添付するのは出来形管理図表と設計図等のみという風に取り決められました。
紙資料に手書きの実測値は不要
これまで臨場では、実測値を確認し、それが設計値と異なれば、資料に手書きで記入して提出していました。
たとえば、発注者支援業務が出来形を確認する際に、基礎の幅が設計値で300だったところ、実際は308あったとしましょう。
そこで”〇〇(氏名)が308と測りました”という風に手書きで紙資料に記入し、それをデータとして扱っていたのです。
出来形とは、工事目的物のうち、すでに完成した部分を指します。
建設業界では工事の目的物の完成した部分(出来形)に相応する請負代金を支払う出来高払いが採用されているため、出来形管理を通じて施工状況を確認し、発注者の意図通りに目的物が仕上がっているか調査します。
しかし、今回の土木工事電子書類スリム化ガイドでは、手書きの実測値は不要と取り決められました。
では実測値はどのようにして示すかというと、あくまで電子的な方法で記録することとされています。
タブレットを用いた記録や、現場でメモした実測値を後にテキスト機能などを活用して記録し、あくまでアナログな形でのデータは残さないこととなりました。
紙資料のデータを提出すると、後にスキャンなどの手間が発生するため、最初からデジタルで記録を取ることになったのですね。
簡素化の取り組み6: 品質証明書の添付書類は提出不要

品質証明書とは、工事で使用される材料などの品質を証明するための書類です。
従来は品質証明書に、メーカー側の試験成績報告書や製品カタログなどを添付して提出することが多くありました。
特に土木工事の場合は、使用される材料の種類がそもそも少ないため、添付資料を不必要に多く添付してしまう傾向があったのです。
しかし品質証明に関する添付書類は一切不要という風に取り決められました。
簡素化の取り組み7: 休日・夜間作業届の提出について

従来、休日や夜間に作業をする際は、作業届の事前提出が必要とされていました。
しかし現道上の工事であれば、正式な作業届ではなく、次の4つが把握できる週間工程表などの資料提出で作業が可能となりました。
- 作業日
- 作業時間
- 作業場所
- 作業内容
なお、こちらは作業日ごとに提出する必要はありません。
たとえば今月は毎週土曜日に作業を実施すると決まっているならば、作業日を集約して提出しても良いとされています。
さらに、現道上の工事以外の工事であれば、週間工程会議やASPによる監督職員への事前連絡のみで可となります。
ASPとは、Application Service Providerの略称で、業務系アプリケーションソフト機能をインターネット経由で顧客や事業者へ提供するサービスのことです。
現道とは、現在主に使用されている道路のことを指します。
その他、道路には新道と旧道もあります。
新道は新しく作られた道のことで、旧道は新道がゆくゆく現道になった際、古くなった方の道路のことです。
旧道は廃道とされる場合もありますが、ときに生活道路として活用され続ける可能性もあります。
簡素化の取り組み8: 排出ガス対策型・低騒音型建設機械の写真は不要

国土交通省では、排出ガス性能の良い建設機械を”排出ガス対策型”として、また、騒音・振動が相当程度軽減された建設機械を”低騒音型”として指定しています。
その上で、工事において機械化施工が環境に与える負荷の軽減を目的とし、それぞれ指定機材の使用を推進しています。
そのため、これまでは指定を機材を使用しているという証明用の写真を撮影する必要がありました。
しかし監督職員や現場技術員が現場で稼働している建設機械を確認していれば、写真撮影は不要となります。
監督職員や現場技術員側は、写真の提出を求めないようにとも記載されています。
簡素化の取り組み9: 安全教育・訓練等の実施状況資料は提出不要

安全教育や安全訓練を実施した場合、受注者はその実施状況を記録しますが、その資料は監督職員の請求がない限り、提出が不要となります。
すなわち、資料作成や確認自体は行うものの、確認を証明するための証拠資料を提出する必要はないということです。
それは『取り組み4』で取り上げた作業員名簿などについても同様です。
簡素化の取り組み10: 創意工夫・社会性等に関する実施状況は10項目まで

通常、工事を行う際は、施工会社が工事で取り組むべき創意工夫を役所へ提出することとなっています。
項目数についてはこれまで制限が特になく、したがって工事成績評定で点数を上げたい業者は、より多くの項目を提出していました。
そこで、”自ら立案実施した創意工夫や技術力”および”地域社会や住民に対する貢献”の評価項目については、1工事につき最大10項目までとされ、資料も簡潔に作成するよう取り決められました。
よって、たとえ10項目を超えた提出をしても認められない上に、工事成績評定においても追加の評価はされないこととなります。
自社の取り組みを多く提出するために労力を使い、書類を増やすのは本末転倒であろうということでしょう。
簡素化の取り組み11: 書類検査の検査書類限定型の採用

こちらは書類のスリム化というよりも、書類検査にかかる工程のスリム化というテーマになります。
工事書類がたとえば全40種類あったとすると、従来は検査職員側が40種類の書類をすべて検査していました。
その点を検査書類限定型に変更し、今後は10種類の書類に限定して検査を行う流れとなります。
検査技術館は技術検査時に下記の10種類に限定して資料検査を実施します。
- 施工計画書
- 施工体制台帳(下請引取検査書類を含む)
- 工事打ち合わせ簿(協議)
- 工事打ち合わせ簿(承諾)
- 工事打ち合わせ簿(提出)
- 品質規格証明資料
- 出来形管理図表
- 品質管理図表
- 品質証明書
- 工事写真
工事書類は原則、提出時に確認される他、発注者支援業務の職員や役所の職員によって都度確認が行われています。
したがって、検査時にすべての書類を再度確認することは2度手間であり、非効率であると今回見直されることになったのです。
国土交通省において工事書類がそもそも多いという認識があったからこそ、書類検査の工程もスリム化されたと言えるでしょう。
まとめ
今回は、国土交通省が推進する工事書類スリム化の取り組みを2記事にわたって解説しました!
紹介した取り組みは次の通りです。
- 工事着手前の設計審査会で役割分担を明確化
- 施工計画書の提出と内容について
- 工事打合せ簿の添付資料について
- 施工体制台帳の添付資料は必要最小限にする
- 臨場確認の写真は添付不要
- 品質証明書の添付書類は提出不要
- 休日・夜間作業届の提出について
- 排出ガス対策型・低騒音型建設機械の写真は不要
- 安全教育・訓練等の実施状況資料は提出不要
- 創意工夫・社会性等に関する実施状況は10項目まで
- 書類検査の検査書類限定型の採用
工事書類のスリム化は、工事書類をチェックする側である発注者支援業務にとっても大きな変革となります。
すべての取り組みが定着されれば、建設業界はより働きやすい環境となるでしょう。
急な環境の変化に慌てないよう、今からペーパーレスの動きへ慣れておくことをオススメします。
この記事の内容は以下の動画で解説しています。
理解を深めたい方はこちらの動画もご覧ください。