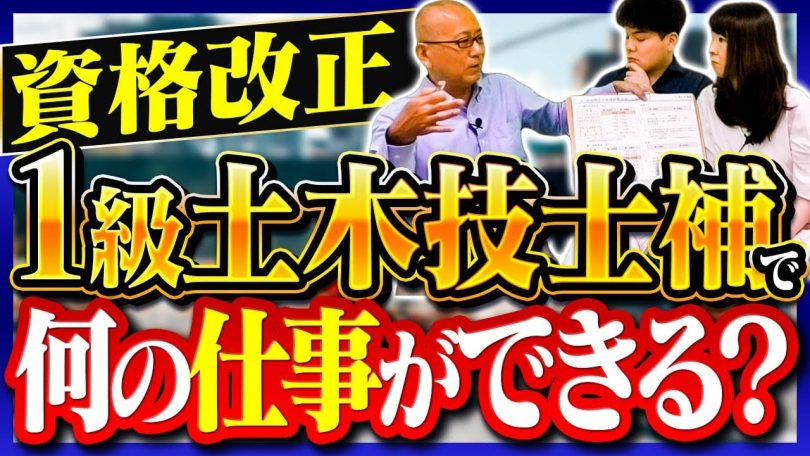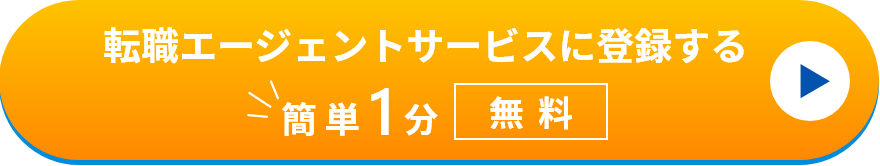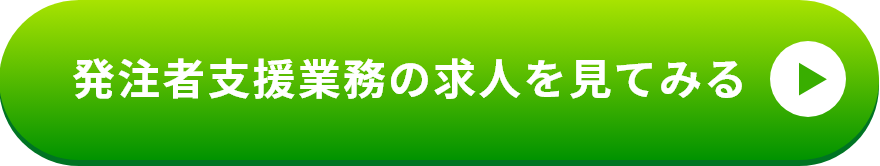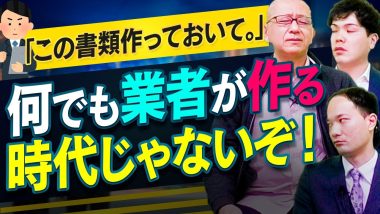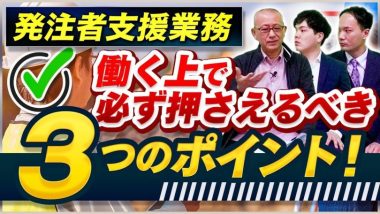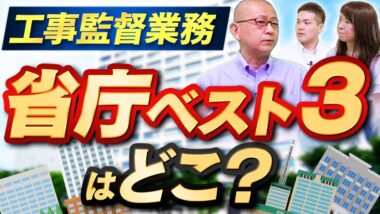工事監督業務のリモート事例5つ!遠隔臨場はどんな工事で使われる?

この記事は以下の記事の続きです。
前の記事を読んでいない方は、こちらの記事もご覧ください。
令和4年度より本格導入されたリモートによる遠隔臨場。
すでに遠隔臨場の効果・効率化が認められた事例が続々と上がってきています。
そこで今回は遠隔臨場を通じて具体的にどのような効果があったのか、実際の事例を5つ紹介します。
目次
遠隔臨場の事例1:伐木除根工の伐木範囲確認
が効果的って言うけど、実際どんな感じ?【リモート確認、事例集】-1-8-screenshot.png)
工事前の伐木・除根がきちんとなされたかという確認を、リモートによる遠隔臨場で行った事例です。
伐木・除根の確認は、平たく言えば「全部刈り取れているか」をざっくりと確認できれば良いので、遠隔臨場に適していると言えるでしょう。
また、工事前に伐木、除根を行うくらいの場所であれば、交通の便もあまり良くないと推測されます。
その上、同事例に関しては工事実施箇所が全体で16箇所とのことで、通常であれば移動だけで大変な時間と労力がかかるはずです。
よって、こちらはまさに遠隔臨場に適した典型例という感じですね。
遠隔臨場の事例2:掘削工における岩質判定検査
が効果的って言うけど、実際どんな感じ?【リモート確認、事例集】-2-2-screenshot.png)
掘削による岩質検査をリモートによる遠隔臨場で行った事例です。
ダムや河川、砂防工事の場合、掘削を行いどこで岩質が出てくるかを確認しなければなりません。
岩質の発生により、コストや設計変更にも影響があるからです。
あらかじめ設計図の中に岩質のラインが記載されて場合もありますが、掘削をしての現場調査も必須となります。
ちなみに、通常の岩質判定検査の流れは次の通りです。
- 岩質が出てくる
- 岩質を露出させる
- 監督職員に見てもらう
さらに横断図などの図面に「こういう状態で岩が入っていた」と情報を記入しなければいけないため、スタッフを立てて調査します。
基本的にその間、工事はストップとなります。
岩質判定検査の難しさは、いつ発見されるかタイミングが読めないことです。
埋設排水管などは既設図面があれば事前に場所がわかりますが、岩は掘削してみないとわかりません。
よって、このように日程の目途が立たないものは、遠隔臨場が非常に効果的となります。
特に同事例はダム工事ということもあり、かなり山奥の現場であると推測されます。
事務所から現場までの移動時間や、岩質の発見がいつになるかわからない点を加味すると、遠隔臨場の寄与度は高いでしょう。
砂防とは地すべりやがけ崩れなど、土砂災害対策を目的とした手段の1つです。
日本は国土面積の7割を山地が占める上、山に囲まれた谷地やその下流で開けた扇状地、火山周辺の台地を生活や産業活動場所としているため、このような場所を守るための”砂防”という技術が非常に発展しています。
世界でも”sabo”という言葉がそのまま通用するくらいです。
遠隔臨場の事例3:場所打杭工の鉄筋組立完了時段階確認
が効果的って言うけど、実際どんな感じ?【リモート確認、事例集】-3-55-screenshot.png)
場所打杭とは、地中に深い穴を掘り、その穴に組み立てた鉄筋を収める作業です。
この事例は、鉄筋が組み上がった段階で検査する際に、遠隔臨場を活用したものです。
同事例を担当した施工者(受注者)のコメントから、その効果のほどがわかります。
「施工条件により立会時間がはっきりしない場合において、スムーズに立会を行うことができ、作業を止めることなく施工を進めることができた」
“施工条件により立会時間がはっきりしない場合”と書かれていますね。
場所打ち杭いの鉄筋は、いわゆる通常の鉄筋を組み上げて型枠を組む工法とは異なり、丸く筒状で”鉄筋かご”と呼ばれています。
鉄筋かごでは、型枠の中に鉄筋を組むのと工事の進み具合が違うのです。
要は前項の岩質検査と同じで、”いつ”のタイミングがはっきりしない検査ということになります。
したがって、リモートの遠隔臨場であれば、移動時間や流動的な立会時間に縛られることがなく、待ち時間が発生した際には他の事務処理などを行えるなど、より効率的だと言えるでしょう。
遠隔臨場の事例4:法面工の出来方・品質確認
が効果的って言うけど、実際どんな感じ?【リモート確認、事例集】-5-36-screenshot.png)
法面とは、斜面のことです。
つまり、こちらは斜面の現場における出来形・品質確認をリモートによる遠隔臨場で行った事例となります。
どのような効果があったのか、先に担当施工者(受注者)のコメントを見てみましょう。
「高所等、直接目視が困難な箇所での監督職員による確認が容易に行えた」
“高所等、直接目視が困難な箇所”とありますので、これもリモートによる遠隔臨場が効果的な典型例です。
実際に作業をしている人がいる以上、点検も可能ではあるのでしょう。
しかし臨場を行うのはこのような現場に慣れている作業者ではなく、通常の監督職員です。
よって、法面の臨場にかかる不安や危険を考えれば、やはりリモートによる遠隔臨場の方が圧倒的に良いということになるでしょう。
遠隔臨場の事例5:舗装工出来形・品質確認
が効果的って言うけど、実際どんな感じ?【リモート確認、事例集】-2-2-screenshot.png)
こちらは道路のアスファルト舗装の出来形・品質確認をリモートによる遠隔臨場で行った事例です。
担当施工者(受注者)のコメントは次の通りです。
「立ち合い場所・時間帯の成約が少なくなった」
“時間帯の成約”とありますが、こちらは夜間の立合検査のことです。
道路が現場の場合、既存道路を完全に封鎖することは難しいため、交通量の少ない夜間に工事を行うことが多いのです。
しかし遠隔臨場になったからと言って、夜中に行っていた検査が昼間になるわけではありません。
夜間立会における遠隔臨場の最大のメリットは、移動時間を削減できることです。
例えば22時に立会があり、役所の事務所から現場までの移動で約1時間を要するとしましょう。
そして立会に30分かかり、また1時間かけて事務所に戻ってきたと想定すると、事務所に着く頃には23時半。
つまり「終電がない」「泊まらないといけない」という事態になりやすいのです。
これがリモートによる遠隔臨場であれば、22時に遠隔臨場で立会を行い、22時半で終了、そのまま帰宅することが可能になります。
コメントにあった”立ち合い場所・時間帯の制約”には、このような監督所員が帰宅する際の足の問題も含まれているのです。
しかしWebになれば移動時間を削減し、このような問題発生も回避できるということになります。
実例から見る遠隔臨場の効果
が効果的って言うけど、実際どんな感じ?【リモート確認、事例集】-8-1-screenshot-1.png)
遠隔臨場はそもそも、場所・時間の制約からある程度解放されることで、作業が非常に効率的になると言われていました。
しかしこうして実例を見ると、“移動時間”への寄与度が圧倒的に高いことがわかります。
特に複数現場を抱えているような場合は、数時間の移動時間の削減も可能となり、遠隔臨場の効果が大きく発揮されるでしょう。
まとめ
今回は、令和4年4月より本格的にスタートされた遠隔臨場の実例を5つ紹介しました!
今後はこのようなリモートによる遠隔臨場・確認がより一層主流となってきます。
発注者支援業務で、特に工事監督を務める人は今から積極的に遠隔臨場に慣れていきましょう。
/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/
「完全土日休み」発注者支援業務の仕事探しなら!
▶発注者支援業務ナビ
「どんな仕事なんだろう?」まずは転職相談から!
▶発注者支援業務エージェント
「土木技術者が集まらない…」とお困りの企業様に!
▶発注者支援業務ナビ求人掲載
_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/
この記事の内容は以下の動画で解説しています。
理解を深めたい方はこちらの動画もご覧ください。